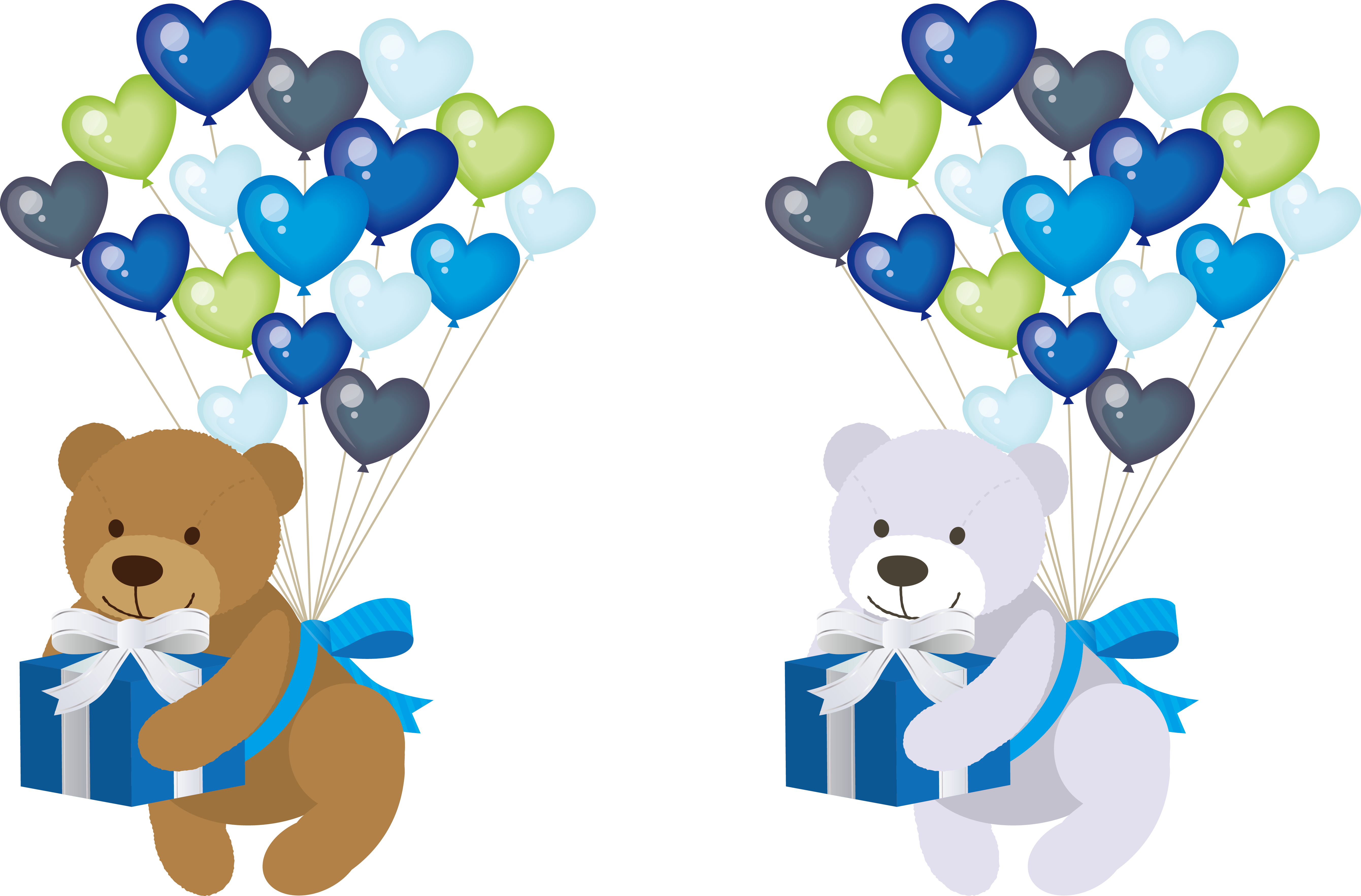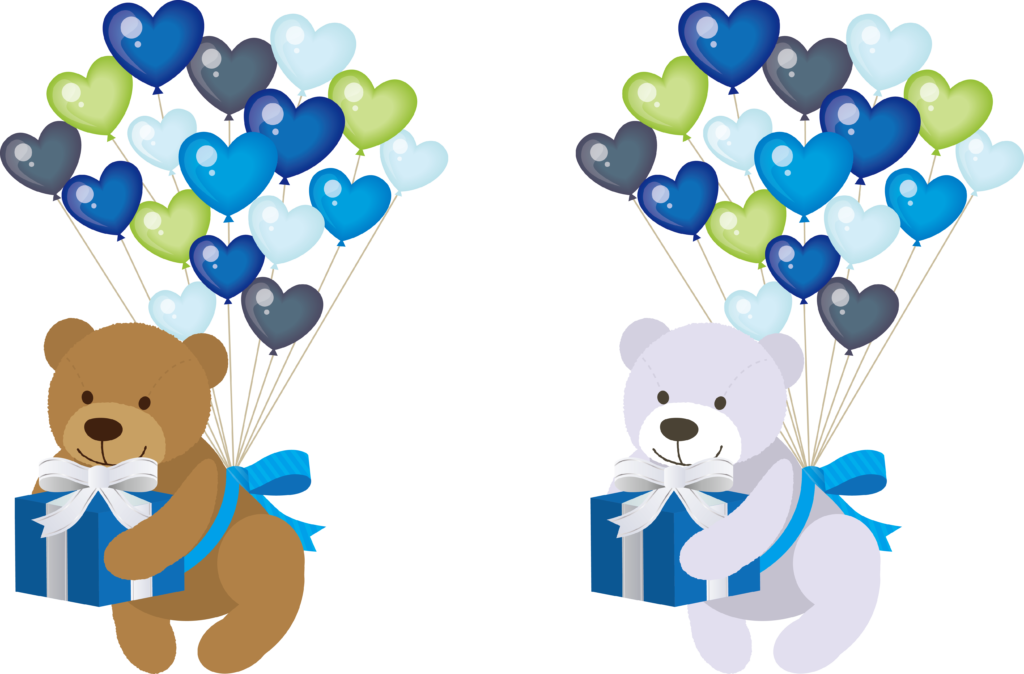
株式・ETFの贈与は相続対策として効果的です。
特に株式・ETFは贈与時の評価額が選択できるので、株価急落時は贈与には絶好のタイミングとなり、次世代に資産を多く残すチャンスとなります。
[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]- 株が急落したけど、何か対策はない?
- 株を贈与する時の注意点は?
- 株の贈与の手続きはどうやるの?
株式・ETFを保有していて相場急変で困っている方、次世代への承継を考えている方向けに記事をまとめました。
株式・ETFの贈与は評価額が選択できるので株価急落のピンチをチャンスにできますし、長期に取り組むことで相続対策として効果的なので、子供や孫にきっと喜ばれます!
取引のある金融機関や税理士に相談し、できる対策をしていきましょう!
(本記事は一般的な税制の話です。詳しくは税理士、税務署にご確認ください)
株式・ETF贈与が相続対策として有効な理由3点
[box class=”box26″ title=”ポイント”]- 時間を味方に 長期に対策ができる
- 値上がりと配当が期待できる
- 贈与の評価額を選択できる
(株式とETFは同じ考え方です。以後、株式で統一しています)
時間を味方に 長期に対策できる
相続は亡くなった時の1回で資産を承継し課税されますが、贈与は毎年できるので時間を味方にできます。
ただし、贈与税は相続税よりも負担が重くなるため、一度に多額の資産を渡した場合、贈与が不利になることがあります。
贈与税率と相続税率を考え、毎年の贈与額を検討する必要があります。
贈与税は、20歳以上の子供や孫に贈与する場合(特例贈与)と、それ以外の者に贈与する場合(一般贈与)に分かれます。
ここでは特例贈与で考えてみます。
| 贈与額 | 税率 (控除額) |
上限まで贈与した場合の 贈与額 |
|---|---|---|
| 310万円以下 | 10% | 20万円 |
| 510万円以下 | 15% (10万円) |
50万円 |
| 710万円以下 | 20% (30万円) |
90万円 |
| 1,110万円以下 | 30% (90万円) |
210万円 |
| 1,610万円以下 | 40% (190万円) |
410万円 |
| 3,110万円以下 | 45% (265万円) |
1085万円 |
| 4,610万円以下 | 50% (415万円) |
1835万円 |
| 4,610万円超 | 55% (640万円) |
1835万円超 |
上記表の贈与税額から基礎控除の110万円を引いて、税率をかけ控除額を引きます。
例えば、510万円贈与した場合は、
(510万-110万)×15%-10万=50万円となり、表の右の税額になります。
仮に1110万円贈与しても、210万円の贈与税になり税負担率は18.9%となります。
相続税の場合、資産全部が基準となり相続税率が決まります。財産が多ければ、相続税率が高くなります。
ざっくりですが、自分の相続税率を知り、それよりも低い贈与税率の贈与額を贈与します。
贈与税については国税庁HPからの引用をご参照、以下を開いてください。
[open title=’贈与税の計算(国税庁HPから引用)’]贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※ 「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税の具体的な税額計算
次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。
- (1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合
- (2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合
- (3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
(1) 「一般贈与財産用」の計算
例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。
・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
(2) 「特例贈与財産用」の計算
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
例えば、20歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。
この場合には、次のとおり計算します。
 全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。 全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。 納付すべき贈与税額は、
納付すべき贈与税額は、 と
と の合計額です。
の合計額です。
(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算
 この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…
次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
 この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
500万円 - 110万円 = 390万円
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円 × 400万円 / (100万円+400万円) =38.8万円…
(贈与税額の計算)
 贈与税額 =
贈与税額 =  一般贈与財産の税額 +
一般贈与財産の税額 +  特例贈与財産の税額
特例贈与財産の税額
上記の場合  10.6万円 +
10.6万円 +  38.8万円 = 49.4万円…贈与税額
38.8万円 = 49.4万円…贈与税額
(相法21の2、21の5、21の7、措法70の2の4、70の2の5)
(平成31年4月1日現在の法令等によっています。)
[/open]値上がりと配当が期待できる
株式の経済的メリットとして、「値上がり」「配当」があります。
贈与で最も効果がでるのは、今後値上がりするものは早めに渡すことです。
例えば、今1000万円の株があり、これが20年後に1億になるとします。そのタイミングで相続が発生した場合は、1億が評価額となります。
ですが、1000万円で贈与をしていれば、税負担は1000万円に対する贈与税負担だけで済みます。
また、保有している間に受け取れる配当金があります。20年間あったら相当な額になります。
贈与をしていれば、配当は子供や孫が受け取ります。
子供、孫は毎年配当を受け取る楽しみができ、贈与をしてくれた親や祖父母に感謝します。
この点から、株式贈与は税金だけでなく、子供に対しての経済メリットも満たせる、最高のスキームと考えます。
(株価は変動し、配当が必ずあるとは限りませんのでご注意ください)
贈与の評価額を選択できる
これは株式・ETF特有の評価方法です。
評価額を以下の4つの中から有利な評価額を選ぶことができます。
上場株式を贈与する場合の評価額は次のうち最も低い価額を使えます。
- 課税時期の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
株式が急落した局面では、急落した月を確認して、その月の株価を使える、後出しじゃんけんができます。
例えば、5月11日に贈与を実行する場合、以下となります。
- 5月11日の終値
- 5月の毎日の終値の平均額
- 4月の毎日の終値の平均額
- 3月の毎日の終値の平均額
2020年3月は新型コロナの影響で株価が急落しました。この3月の毎日の終値平均が使えるのです。
株式贈与はメリットが多い方法と思います。
ただ、メリットばかりではありません。デメリットや注意点もありますので、次でご説明します。
株式贈与のデメリット・注意点等
株価下落リスク
株・ETFは変動しますので、贈与した後に下がることもあります。贈与時よりも相続時に株価が下がっていたら、贈与しないほうがよかったことになります。
しかし、一度に多額の株式を贈与せずに、毎年贈与するのであれば、ドルコスト平均法の考え方ができ株価の変動が平均化されます。
また、前述したように、株価急落後であれば評価額の時期を選べるので、下落リスクは大幅に減らせると考えます。
贈与税負担
贈与税は現金納付です。
受贈者は手持ちの現預金で納税が必要です。手元資金がない場合は、株式と一緒に現金も贈与してもらうことが考えらえれます。渡した現金も贈与の対象になります。
また、贈与は受け取った人(受贈者)を基準に考えますので、父と母からもらった場合は、受贈者が合算して贈与税を計算することになります。
相続発生から3年以内の贈与
相続から3年以内に贈与した資産は、相続時の計算上、相続財産に戻して計算します。つまり、贈与がなかったことになります。
すでに納税した贈与税は、相続税から引かれますので、納税しすぎにはなりません。
相続税の計算の際の評価額は贈与時の価格になるため、贈与時が低い株価であれば有利となります。逆に高い株価だと不利です。
孫への贈与
孫への贈与は、上記の3年以内の相続時の持ち戻しはありません。
例外として、孫も相続時に財産を受け取る場合は、相続時の持ち戻しの対象となります。
譲渡税はかからない
贈与により株式が移動しますが、譲渡税はかかりません。
受贈者が、今後、譲渡する時に譲渡税がかかります。
その際の、取得費は贈与者の取得費を引き継ぎます。
インサイダー取引規制
贈与はインサイダー取引規制対象外となっています。
役員の方でインサイダー情報を持っていても、いつでもできるということです。
今後、業績UPの情報を持っていれば、株価の値上がりの期待があります。情報開示前に贈与すれば、値上がりする前の株価で贈与できるということです。
ただ、インサイダー取引規制の判断は難しい場合がありますので、インサイダーフリーのタイミングで贈与する方も多いようです。税理士や弁護士等専門家によくご相談ください。
投信の贈与は評価額を選べない
同じ有価証券でも投資信託は評価額を選択できません。
前述した贈与時の評価額を選べるのは、株式・ETFになります。
特定口座で受ける場合
これ注意が必要です。
パターンがいくつかあるので、パターンで解説します。
| 受贈者 | |||
| 特定口座 贈与株保有 |
特定口座 贈与株未保有 |
||
| 贈与者 | 特定口座 一部の株式贈与 |
✖ | 〇 |
| 特定口座 全部の株式贈与 |
〇 | 〇 | |
受贈者がすでに贈与される株式を特定口座で保有している場合、贈与者から株式の一部を贈与で受けられません。
受贈者がすでに特定口座で株式を保有している場合は、以下のいずれかの対応となります。
- 贈与者が残りの株式を全部贈与する
- 受贈者が他の証券会社で特定口座を作り、贈与を受ける
- 受贈者が一般口座を作り、贈与を受ける
また、贈与者が一般口座で株式を保有している場合、受贈者の手続きは証券会社で異なりますので、お手続きする証券会社に確認が必要です。
贈与しすぎてしまうこと
贈与すると自分の資産が減少します。贈与しすぎると、株の値上がりや配当金を受け取る楽しみがなくなります。
贈与しすぎて、老人ホームに入る資金がなくなった、という笑えない話を聞いたことがあります。
また、子供が複数人いるのに、特定の子供に偏って贈与していると、相続時の争いの種になります。
バランスを考えた贈与が必要です。
遺留分に注意
相続が発生した際、相続税の計算では3年以内の贈与は持ち戻して計算とお伝えしましたが、それと似ています。
相続の時には、相続税とともに財産分割が必要です。
財産分割では、相続人が最低限受け取る権利(遺留分侵害額請求権)があります。
遺留分侵害額請求権では贈与財産は10年分戻して計算します。
その際、対象となる額は贈与時の株価ではなくて、相続時の株価となります。贈与から相続までに株価が大幅に上昇していた場合、注意が必要です。
やはり、偏った贈与をすると相続の争いの種となります。
手続き
証券会社手続き
[box class=”box26″ title=”ポイント”]- 株式を預けている証券会社に連絡
- 受取側の証券口座が必要
証券会社によって手続きが異なりますので、まずは贈与する方がお取引の証券会社にご相談してください。
受取側は贈与者と同じ証券会社でも、別の証券会社でも株式を受け取ることができます。
贈与申告
[box class=”box26″ title=”ポイント”]- 翌年に、
- 贈与を受けた人が、
- 贈与申告・税納をする
贈与を受けた翌年に、贈与を受けた人(受贈者)が贈与税申告と納税を行います。
受贈者が納税しますので、納税資金が必要です。手元資金がない場合は、株式と一緒に贈与税納税資金も贈与する必要があります。
(贈与者が贈与税を支払うと、それ自体も贈与の対象になりますのでご注意ください)
まとめ
[box class=”box26″ title=”タイトル”]- 時間を味方に 長期に対策ができる
- 値上がりと配当が期待できる
- 贈与の評価額を選択できる
- 各種、手続き注意点があるので専門家に相談する
長期に、株式の特性を活かした資産承継が可能です。
相場急変時でも、できる対策として富裕層の方が行っています。
証券会社や税理士に相談し、うまく資産承継していきましょう。
税理士にも専門分野があります。相続税・贈与税に強い先生にご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございます!
ぜひ他の記事もご参考ください。