
銀行のリテール部門で働いている方、これから働く方におすすめする資格7選です!
[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]
- 銀行で働くのに、どんな資格が有利なの?
- ステップアップにはどんな資格が有利なの?
と気になっている方に参考になる記事を書きました。
実際、私は銀行に勤めていて、資格取得をうまくキャリアのステップアップに活かしてきました。
その経験からご紹介させていただきます!
資格取得を検討される方の参考になれば幸いです!
目的 資格取得の目的は何?
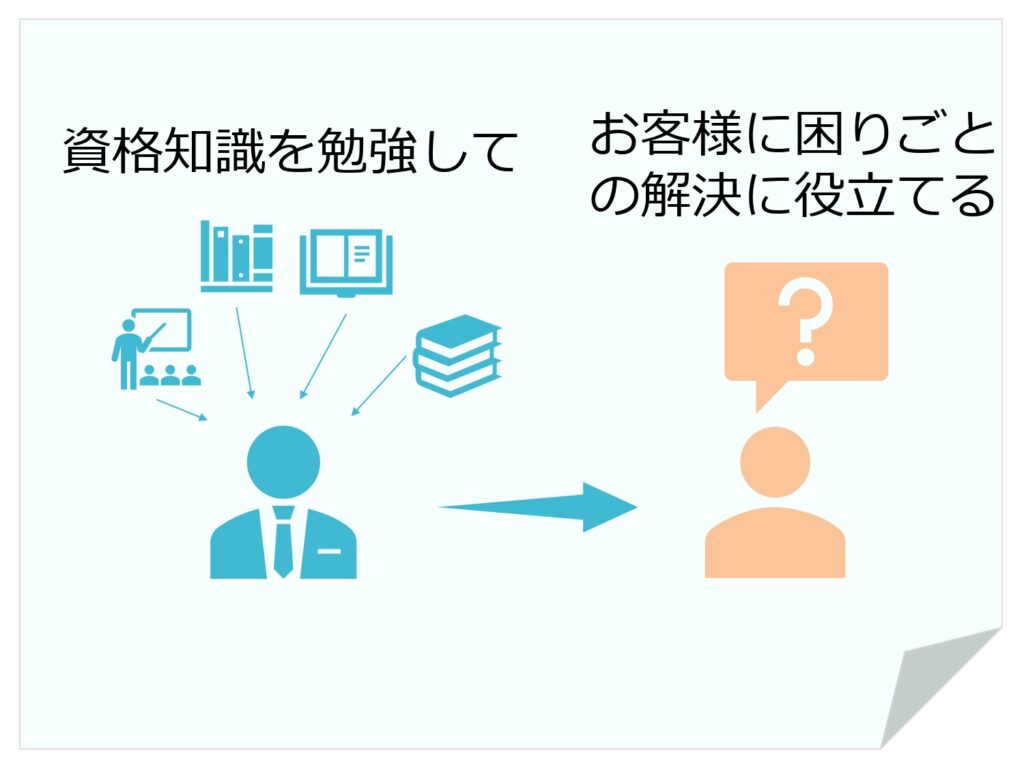
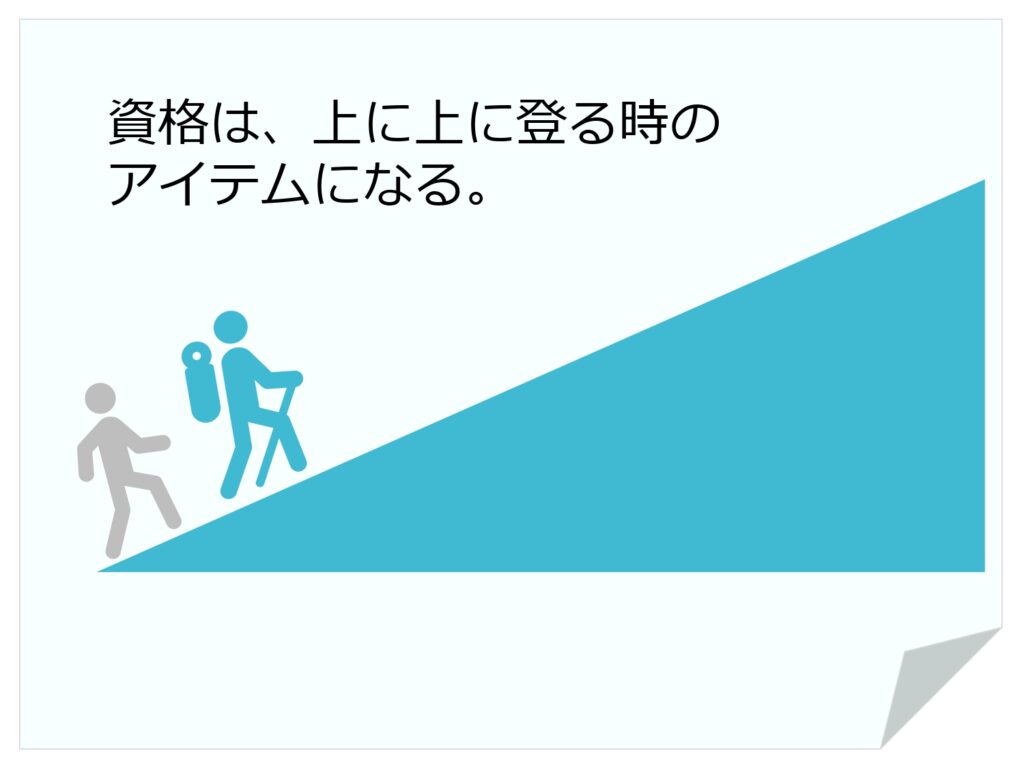
- 仕事に役立てたい
- キャリア形成に役立てたい
- 昇格に役立てたい
- 収入アップに役立てたい
等々あるかと思います。
銀行は物を売らない知識を武器に戦うコンサルに近いです。知識産業なので知識は武器になります。
多くの知識を身に着ければ、お客様の悩み事の解決方法をいくつも思いつくことができます。
研修や日々の業務で学んだり、新聞で知識を得ることもできますが、それだと周りの営業マンと同じです。差別化をするためにもプラスアルファの知識が必要です。資格の勉強をすることでプラスアルファの知識がつくと思います。
資格はその分野を網羅的、体系的に学べるので理解が深まります。理解が深まるとお客様に説明する時にわかりやすく、説得力がついて説明ができるようになります。
その点で、資格を勉強し取得することは仕事に役に立ちます。
そうして、お客様へ高いレベルの提案ができると、それが経験となりキャリア形成につながります。
キャリア形成ができ、昇格ができると収入アップにもつながるというステップが考えらます。
残念ながら資格を持つことで、直接、昇格や年収UPにはつながりません。
私は当初資格に興味がなかった時は、資格手当があるのかな、と思っていました。
しかし、調べたら資格手当はでないとわかり愕然とした記憶があります。
合格時にわずかばかりの奨励金が出るだけです。
銀行では昇格して役職が付いたり、管理職になれば年収がUPします。
では、資格があると昇格しやすいか、管理職になりやすいか、というとそんな事はありません。
銀行の昇格とは、経営層(支店長や部長、果ては役員)になっていくことを意味します。
経営層に必要なのはマネジメント能力です。
マネジメント能力は資格試験のように座学で身に着くものではなく、その人の能力と業務経験でつくものです。
銀行の資格保有の詳しい統計は知りませんが、経営層ほど資格保持者は少なくて、経営層ではない担当者の方が資格保持者が多いのではと感じます。
こんな話をすると、資格があっても昇格できないのかとなりそうですが、私はやはり資格は武器・アイテムになると思っています。
例えば上の図の登山でイメージをお伝えします。
目標となる頂きがあって、頂きまで登るのに、何も持たずに登るのと、ちゃんとした登山靴や杖を持って登るのでは、後者のほうが早く登れると思います。
この登山靴や杖が資格です。
資格があると早くスムーズに上に上にいけるのではと思います。
ただ、中には資格がない、下手したらサンダルなのに登るスピードが速い人がいたりします。
これは致し方ない。。。
私は就職活動の頃から資格を取得することでその分野に興味があるんです、そこに向けて勉強してます、とアピールしてきました。
結果、自分が働きたい、その資格が活かせる部署に異動が出来、周りの同僚に差をつけることができて昇格も早く進みました。
ぜひ、資格を取得だけに終わらせず、仕事に役立て、キャリア形成に役立てていただければと思います。
(ご参考)資格取得について考えた記事です。こちらもご参考ください。
[card2 id=”227″]悩み どんな資格?有利なの?
[box class=”box31″ title=”悩みと疑問”]- どんな資格があるの?
- 仕事の役に立つの?
- 将来の役に立つの?
- 難易度は?
銀行では必ず取らないといけない資格があります。
例えば、証券外務員試験や保険募集人の資格などです。
このブログでは、そういった資格とは別で自己研鑽として取り組む資格を取り上げます。
おすすめの資格を次のところでとりあげ疑問点について独自の判断で評価をしています。
仕事の役に立つかどうか?は、業務に活用できるかという観点で評価しました。
難易度は各資格の情報を基にと、自分で勉強した感覚から評価しました。
★が多いほど難しいとなります。(その分持っていれば一目置かれる)
将来性も独自判断になりますが、銀行以外でも使えるか、今後使えるかという観点で評価しています。
[rate title=”資格の評価”] [value 5]活用[/value] [value 5]難易度[/value] [value 5]将来性[/value] [value 5 end]総合評価[/value] [/rate]金融に関する網羅的な資格
①ファイナンシャルプランナー資格 (1級、2級)
[rate title=”FP2級”] [value 4]活用[/value] [value 3]難易度[/value] [value 4]将来性[/value] [value 5 end]総合評価[/value] [/rate][rate title=”FP1級”] [value 4]活用[/value] [value 4]難易度[/value] [value 4]将来性[/value] [value 5 end]総合評価[/value] [/rate]
FPは必ず取ったほうがいいです。
富裕層を担当される方ならば、1級は持っておきたいところです。
金融について網羅的にカバーしている良質な資格です。大きく6分野に渡ります。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理(いわゆる保険)
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
FP試験は「金融財政事情研究会(きんざい)」が実施している国家資格ファイナンシャル・プライニング技能士と「日本FP協会」が実施しているAFP、CFPがあります。
銀行勤務の方は「きんざいのFP技能士」をお勧めします。
なぜなら、国家資格ですし、継続教育がないので楽だからです。
一方で、日本FP協会のAFP、CFPは継続教育があります。
継続教育があるほうが知識をブラッシュアップできるのでいいという方もいます。
独立系や保険代理店FPなどはこっちを取っている人も多いと思います。
FP技能士とAFP、CFPの比較です。
| FP技能士 | AFP、CFP | |
| 主催 | きんざい | 日本FP協会 |
| 国家資格 | 〇 | ✖ |
| 資格レベル | FP2級 | AFP |
| 資格レベル | FP1級 | CFP |
| 資格試験 | 一度に6科目 | 6科目を 1科目づつでもOK |
| 継続教育 | なし | あり |
| 取得者の傾向 | 銀行、証券 | 独立系、保険会社 |
銀行のFP技能士の取得状況はリテール営業の人でFP2級が20~30%、FP1級で5~10%ぐらいではと思います。
取得は推奨されていますが、個人的にはみんな勉強してない印象があります。
リテール営業はコンサルティング力が必須です。
ライバルは他社だけはありません。
それはAI。AIの発展は金融業界で働く人には脅威のライバルです。
AIに勝つためには、お客様のニーズをいかにくみ取って、最適な提案ができるかです。
その時に網羅的に学べるFPの知識は役に立ちます。
単純な提案ではなく、FP知識を活かしてライフプラニングをベースにしたコンサルティングです。
効率的な貯蓄方法やリスク許容度に応じた金融商品の提案、高い買い物である不動産購入に対するローンの組み方、ライフプランに沿った保険の提案、築いた資産を次世代への承継する方法、等々。
お金に関することを複合的に色々な角度から提案することが大事だと思います。
難易度ですが、金融関係の経験があるとスムーズだと思います。
FP2級だとリテール営業を3年程度経験していれば、なんとなく勉強できる感じだと思います。
FP1級だと5年以上の経験があればいいと思います。
私は1級取ったのは社会人9年目でした。。。おそい。。。
将来像ですが、企業に勤めるいわゆる企業内FP、独立系FP、保険代理店(自営)となります。
FP資格だけでの独立開業は厳しいのではないでしょうか。
税理士等ほかの資格と組み合わせが必要です。
基本的には金融機関に勤める、企業内FPが自分自身のライフプランも考えながら活躍できる場だと思います。
②プライベートバンカー資格 (プライマリー、シニア)
[rate title=”PBプライマリー”] [value 4]活用[/value] [value 3.5]難易度[/value] [value 3]将来性[/value] [value 3 end]総合評価[/value] [/rate] [rate title=”PBシニア”] [value 3]活用[/value] [value 4.5]難易度[/value] [value 3]将来性[/value] [value 4 end]総合評価[/value] [/rate]将来像:金融機関 富裕層担当 外資系
日本証券アナリスト協会が運営している比較的新しい資格です。
FP資格の富裕層に特化しています。
富裕層(資産一億円以上)医者、不動産持ち、中小企業オーナーを担当される人にはいいと思います。
ファミリービジネス、その一族の繁栄最大化のために、資産活用や承継の観点から総合的なコンサルティング能力が身に付く資格です。
一次試験は選択問題でFP1級の知識があれば難しくないと思います。
二次試験が特徴的で提案書作成という試験です。
一次試験に受かると富裕層のプロフィールや課題などが書いたA4資料5枚ほどが送られてきて、それに対しての総合的なアプローチを20枚ぐらいの提案書に落とし込みます。
きちんと顧客ニーズを捉えているか、適切なアドバイスか、税務的な観点等から裏付けある提案か、といったことが評価されます。なかなか面白いです。
資格取得後は継続教育があり2年の間に決められたセミナーなどを受け必要な単位を取得し更新が必要になります。
中には面白いセミナーがありますので、勉強になります。
運用系の資格
③証券アナリスト
活用ランク:B
難易度:A
将来像:金融機関
運用、マーケットに強い人は持っている感じです。ただ、個人のお客さまを担当するにあたって、「理論が~」なんて話してもあまり意味がありませんので、なくても大丈夫だと思います。
承継関連の資格
④事業承継・M&Aエキスパート
活用ランク:B
難易度:C
将来像:金融機関
実はこれ資格の名称が立派ですが、試験自体はそんなに難しくないです。FPを持っていて承継関連の仕事をしている人なら特に勉強しなくてもほぼ楽勝で受かると思います。それなのに名刺にも資格を載せることができるので、承継関連の仕事をしている人はそれだけでお客様からの信頼を得られます。
ただし、やはり簡単なだけあって、たとえば転職で有利になるかというとそういうことはなく、金融機関内でしか有利にならないと思います。
不動産関連の資格
⑤宅地建物取引士
活用ランク:C
難易度:A
将来像:不動産関係の仕事もできます
不動産関連の仕事をしているならぜひ持っておきたい資格です。銀行の場合だと融資の話がついてまわりますが、ただ単に貸す貸さないという話だけではなく、物件そのもの不動産取引におけるポイントがわかっているとお客様からの信頼度は抜群になります。ちなみに合格しても登録をしないと名刺には書けません。
将来的には不動産関連の会社に転職するなら大変有利になります。
法人関連の資格
⑥簿記検定
簿記3級 (リテール営業であれば2級はいらない)
活用ランク:B
難易度:B
将来像:これだけでは・・・。
個人営業を考えると正直使う出番はありません。法人申告書・決算書を見ることもありませんし。ただ、やはり銀行員たるもの、お金の流れの知識はあったほうがいいでしょう。最近はリテール担当者が中小企業オーナーへアプローチする機会が増えてますので、知識があって損はないです。リテール担当者は決算書が読める人は非常に少ないので、読めれば非常に有利になると思います。
簿記の知識だけでは将来は難しいですね。銀行の場合、将来的に取引先に経理担当で出向ということも考えられますが、リテール担当者だとその道はないと考えておいたほうがいいと思います。
⑦プロフェッショナルCFO
活用ランク:C
難易度:A
将来像:資格の名称はCFOなれど、CFOにはなれない
簿記が経理とすると、こちらは財務になります。財務は資金調達(銀行融資、株式発行など)、資本政策、資金運用(投資、M&Aなど)など。企業価値を高めるという観点になります。リテール営業としてはほとんど活用する場がないですが、企業オーナーと話をするときに経理的な話だけでなく、財務戦略を語って企業価値を高める話ができるとかっこいいですね。
将来はCFOとありますが、上場会社で活躍するCFOになるのは無理でしょう。活躍しているCFOは投資銀行やアナリストなどM&Aに携わっていた人が多く、大変優秀な人達です。
まとめ
こう考えると、FPは絶対取ったほうがよくて、いまの会社をやめた時にどういったところに再就職するかを考え、何の勉強をするのか考えたほうがよさそうです。
私はリテール部門が好きですし、独立系FPにあこがれているので、その分野で活用できる知識を高めていきたいと思っています。
ちなみに、「いつか取る」と言っている人は取れません。「〇〇までに取る」としっかりと期限を決めましょう。
色々資格はありますが、長い社会人生活です。毎年1つづつ取れば、10年で10資格です!頑張りましょう!



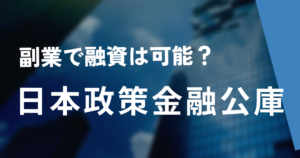



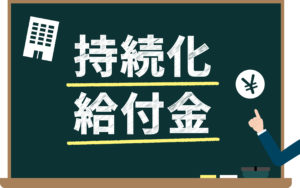

コメント